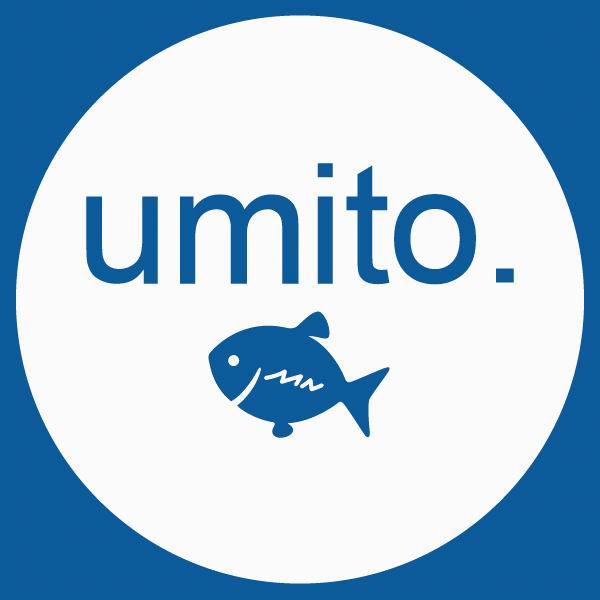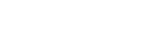2013年に日本人の伝統的な食文化として、和食がユネスコ無形文化遺産に登録されました。数多くの和食の中でも、とりわけ人気の高い食べ物といえば「握り寿司」でしょう。
握り寿司が広く知られるようになったのは江戸時代後期です。当時から天ぷら・うなぎ・蕎麦と並んで、すしは江戸四大名物に数えられていました。すしの中でも握り寿司は、江戸の前にある海川(東京湾)で獲れた海産物を使用したすしの意味で「江戸前寿司」とも呼ばれます。
今回はそんな江戸前寿司についてみていきましょう。
熟れ鮨(なれずし)から握り寿司へ

(発酵ずし 鮒ずし)
江戸前寿司が一般に広まる前、“すし”といえば乳酸発酵を主体とした熟れ鮨(発酵ずし)を指しました。熟れ鮨では、奈良時代以前には作られていたとされる滋賀県の鮒(フナ)ずしが有名です。
しかし発酵には最低でも数か月の期間がかかります。手間ひまを省くために発酵期間を短くする様々な試みがなされた結果、飯を発酵するのではなく、発酵食品のお酢を飯とあわせた「早ずし」へと進化を遂げます。
なお、日本で「すし」の漢字を確認できる一番古い文献は、8世紀半頃に出された『養老律令』で、その中に「鰒鮓二斗。貽貝鮓三斗。」「雑鮨五斗。」という記述がみられます。「鮓」や「鮨」は中国から渡来してきた漢字です。「鮓」は飯と塩を使って魚をつけたもの、「鮨」はみじんにした魚肉のことや、美味を指していました。
「寿司」の漢字が使われるようになった由来や時期ははっきりしませんが、江戸時代に縁起を担いで寿司の字が当てられるようになったといわれています。古くからある熟れずしは「熟れ鮨(鮓)」、江戸以降に知られるようになった江戸前ずしは「江戸前寿司」と書くと雰囲気が出るような気がしますね。
江戸前寿司の種類や値段

(十返舎一九『金儲花盛場』左端に寿司の屋台(客が値段交渉をしている)出典:国立国会図書館デジタルコレクション)
握り寿司の始まりは諸説ありますが、文政年間(1813〜1831年)に、酢をあわせた酢飯の上に魚などの具をのせて販売したことが始まりといわれています。江戸の町は独身男性が多く、彼らを相手にした手軽に食べれる屋台や移動販売が非常に盛んでした。
江戸前寿司のネタには当時から、卵焼き、車海老、海老ソボロ、白魚、マグロ、コハダ、アナゴなど、現在でもおなじみの魚が使われています。
当時は水揚げされた魚介類の鮮度を保つ技術が乏しかったため、ネタを茹でる、蒸す、醤油につけるなど、いろいろな工夫をして食べていました。価格は1貫4文から8文程度で、現在のお金に換算すると120円~240円程度でしょうか。なお、江戸末期で一番高い寿司は、卵巻きの16文だったそうです。
現在と異なる点もあります。まずは大きさです。当時の寿司の大きさは今の2倍以上ありました。大きくて食べにくいために2つにカットしたことが、寿司が一皿2貫になった由来といわれています。マグロは下魚(げざかな)とされ人気がなく、大トロ部分は捨てられてしまう始末。マグロが今のような高級食材になったのは昭和になってからのことでした。
また、マルハニチロ「回転寿司に関する消費者実態調査2023」のアンケートの中で「よく食べるネタ」12 年連続1位の「サーモン」は江戸前ずしのラインナップにはありませんでした。サケ(サーモン)を生食するようになったのは1980年代になってからのことです。この点も現在とは異なっています。
江戸の局地的名物から全国へ
江戸の町で誕生した江戸前寿司が全国に広まったのは、関東大震災や第二次大終戦の後、地方へ移住やUターンした寿司職人が、その土地で店を構えたことが大きな要因です。
また、戦後食糧難の1947(昭和22)年には「飲食営業緊急措置令」の下、ほとんどの飲食店が営業禁止の中、寿司職人だけに客が持参した米をすしに加工する「委託加工」として営業認可を与えられたことも、全国に広がるきっかけとなりました。

(大阪寿司・箱寿司)
江戸時代の東京では寿司といえば握り寿司ですが、大阪ではシャリと具材を重ねて押し固めて作る押し寿司が主流でした。箱の中にすしが彩鮮やかに並ぶ箱寿司は、商家の旦那衆の芝居見物や手土産に最適でした。明治時代以降、もてなし料理や手土産として大阪全域に広まります。

(縞揃女弁慶 安宅の松 出典:東京都立図書館TOKYOアーカイブ)
最後に寿司に関連する浮世絵を見てみましょう。
歌川国芳が天保15年(1844年)に描いた『縞揃女弁慶 安宅の松』です。深川の安宅六間掘(現在の東京・隅田川に掛かる新大橋付近)の「松が鮨」は江戸で一番贅沢な寿司屋でした。
この絵は「松が鮨」からテイクアウトした寿司を子供が「早くちょうだい」とせがんでいる場面が描かれています。ネタは青魚、卵巻き、海老でしょうか。
遠い昔のことにように感じる江戸時代ですが、寿司をとりまく人々の表情は、今の私たちにも通じるようですね。