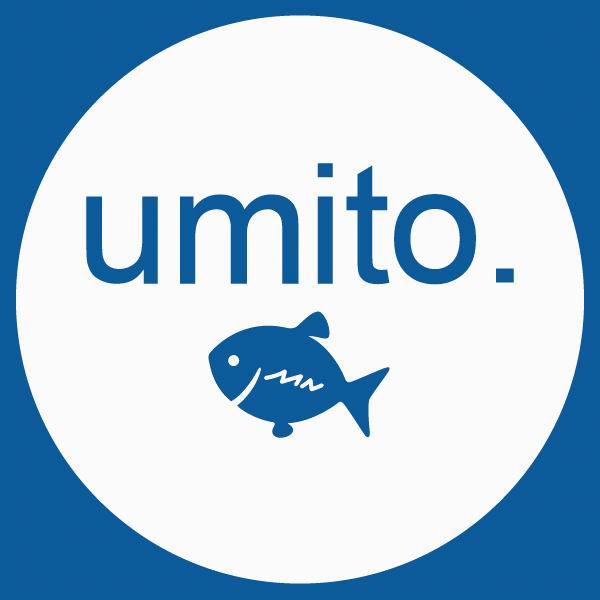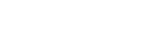醤油の原料と言えば大豆ですが、魚からも醤油ができることはご存じですか?
魚からできる醤油を、日本では魚醤(ぎょしょう)、そして世界では国や地域ごとにそれぞれ固有の名前でよばれています。
タイのナンプラーとベトナムのニョクマムはよく耳にしますよね。ともに「魚の水」という意味です。他にもトゥック・トレイ(カンボジア)、ナムパー(ラオス)、ンガピャーイェー(ミャンマー)、パティス(フィリピン)、魚露(中国)など、さまざまな名前でよばれています。ほぼ同じ製法でありながら、その土地ごとに名前がつくほど、魚醤は世界中で親しまれている調味料なんです。
日本三大魚醤 ーしょっつる、いかなご醤油、いしるー

(しょっつるの主な原料になるハタハタ)
四方を海に囲まれた国、日本にも魚醤があります。秋田のしょっつる(塩魚汁)、香川のいかなご醤油、そして能登のいしる(魚汁)は、日本三大魚醤とよばれています。
しょっつるはハタハタ、いかなご醤油はイカナゴ、いしるはイワシや真サバなどの青魚が原料です。また能登の富山湾に面した内浦地区では、イカの内臓から「いしり」がつくられます。
その地域でよく獲れる海産物を有効利用した調味料なので、タイ、サンマ、サケ、アユなどからつくられる魚醤もあります。どんな味がするのかぜひ味わってみたいですね。
魚醤のうま味のひみつ
魚醤は生の魚を塩に数カ月~数年間じっくり漬け込み、液体部分を集めたシンプルな発酵調味料です。素朴な製法ながら、なぜあれほど濃厚なうま味が生まれるのでしょうか。
そのわけは、魚を漬け込む過程で、内臓や身に含まれる酵素が魚自身のタンパク質を分解し、うま味の元であるアミノ酸やペプチド(アミノ酸がいくつか結合したもの)をつくり出しているから。
大豆醤油には大豆由来のアミノ酸であるグルタミン酸が突出して含まれていますが、魚醤にはグルタミン酸以外にもリジン、アルギニン、それに核酸由来のイノシン酸などが幅広く含まれており、それらの相乗効果でうま味が飛躍的に増強されるのです。
アジアの魚醤と稲作文化

(ベトナムでの魚醤作り)
雨季にたくさん獲れる小魚を保存するために生まれた魚醤は、主に米を主食とする東南アジアで広く使われています。米と野菜が中心の食卓では、魚醤は塩味とうま味を持つ相性の良い調味料です。
ヨーロッパなどの牧畜文化圏では、家畜が子を産んだ時期しか得られない乳を保存しようとチーズやバターをつくり出しました。稲作文化圏における魚醤は、チーズやバターと同じ目的でつくられたのかもしれません。
日本における魚醤と醤油

(左:醤油 右:魚醤)
国内での魚醤のもっとも古い記録は、平安時代の「延喜式」や「倭名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)」に残っており、中国大陸から製法が伝わったとされています。
うま味豊かな魚醤ですが、日本では次第に大豆をはじめとした穀物醤油の使用量が、魚醤の使用量を上回りました。これは奈良時代の仏教伝来とともに肉食が禁じられ、動物性食材が避けられたことや、大豆醤油の繊細な香りや風味が、刺身や豆腐といった食材そのものを生かす日本食と相性が良いためといわれています。
また、穀物から醤油をつくるために、麹(こうじ)カビ、酵母、乳酸菌を絶妙なバランスでコントロールする高度な技術が発達したことや、製法が日本の気候に適していたことも大豆醤油が広まった理由だと考えられます。
初めて魚醤を使う方に
近年、魚醤のおいしさが再認識されています。特に国内産の魚醤は海外産に比べまろやかで、おみやげやお取り寄せ品としても人気が高まっています。ぜひ一度ご賞味あれ。
魚醤には魚が腐敗しないように大量の塩が使われています。そのため大豆醤油に比べて塩辛いので、うま味を生かした隠し味として使うと効果的です。鶏もも肉を焼く前に醤油・にんにく・酒・魚醤に漬けたり、野菜炒めの仕上げにひと振りしたりなど、少量から試してみてください。生臭い匂いを消す作用もあるので、さっと塗って焼いた魚にレモンを絞った焼き魚もおすすめです。

(ナンプラー)
大豆醤油に比べ、含まれるうま味成分の種類が豊富な魚醤は、たった1滴の中に奥深い風味を秘めた調味料。
シンプルな原料だけでつくられた魚醤は、大豆・小麦アレルギーで大豆醤油が使えない方でも使うことができます(ご使用前には原材料をご確認ください)。大豆醤油の代わりには、だしで割ると使い勝手が良くなりますよ。
ちょっと使うだけで、コクとうま味を深めてくれる昔ながらの調味料、「魚醤」を上手に取り入れて、普段の食事に変化をつけてみませんか?